投資信託とは
そもそも投資信託って何?
株式に投資するのは怖いけれど、定期預金ではちょっと物足りない・・・、そんなことを考えたことはありませんか?そんなみなさんにおすすめなのが「投資信託」です。少額から投資できて、その投資先はさまざま。プロの手によって運用される「投資信託」が今注目されています。
投資信託とは
投資信託とは、たくさんの人から集めたお金をひとつにまとめて、運用のプロが株式や債券などに投資し、そこで得た利益を投資した人に投資割合に応じて配分していくことを目的とした金融商品です。
多くの人のお金を集めてひとまとめにし、運用のプロ(ファンドマネジャーといいます)が投資先を決定し運用を行い、そこで出た利益を出資した額に応じて、配分するのが投資信託です。
そのため、投資信託は、投資をしたいけれども自分だけでは多くの株式や債券を買うほどの資金はない、自分ではうまく投資できないので運用のプロに運用を任せたい、そんな人に最適な商品といえます。
そもそも株式や債券は値上がりが期待できますが、一方で値下がりの危険もあります。そこで投資信託では、みなさんのお金をまとめて、数多くの株式や債券などに投資します。それぞれは違う値動きをしますから、たくさんの種類を組み入れることで、分散効果が働き、投資のリスクを少なくすることができるのです。これが、投資信託の最大のメリットです。
欧米では「投資信託はあらゆる投資家の要求に応えられる商品である」といわれています。日本でも、約6,000本のさまざまな投資目的の異なる投資信託が存在しています(2024年12月末時点、国内公募追加型株式投資信託)。値上がり益を追求するタイプのものや、1つの投資信託の中で株式や債券など複数の資産を組み合わせるタイプ、安定した利回りを重視するタイプなどです。また、最近話題の新興国の株式に投資するタイプや、オプション(ある金融商品を将来の一定期日、または一定期間内に売買できる権利)や先物取引(将来の一定期日に受け渡しする商品の約定価格を現時点で取り決める取引)などデリバティブ(金融派生商品)に投資するタイプなど、個人では直接投資することの難しい投資対象に投資する投資信託もあります。
こういった投資信託の特徴を最大限に活かしながら、いろいろなタイプの投資信託に投資してみてはいかがでしょうか?
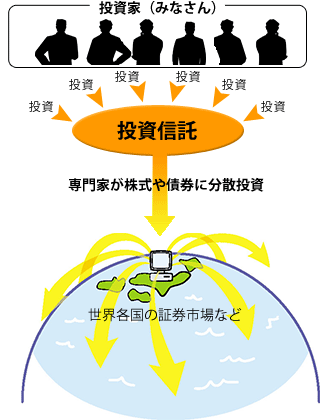
「投資信託とファンド」って良く耳にするけどどう違うの?
投資信託の情報を集めていると、「ファンド」という言葉がよく出てきますが、「投資信託」と「ファンド」は同じものなのでしょうか?
「ファンド」は、投資信託以外の金融商品についても指す場合があります。
「ファンド」と「投資信託」の大きな違いは、「投資信託は行政の監督を受けた投資信託委託業者によって厳しい監督の下で運営されている」点にあります。
「ファンド」とは一般にはみなさんから集めた資金の運用を投資顧問会社などの機関投資家が代行する金融商品を指し、次のような商品があります。
- 公募投資信託
- 特定金外信託(特金)
- その他(匿名組合、リミテッド・パートナーシップなど)
投資信託も投資信託以外のファンドも、みなさんのお金を集め、いろいろなものに投資するという意味では同じものですが、その監督体制に大きな違いがあります。「投資信託は行政の監督を受けた投資信託委託業者によって厳しい監督の下で運営されている」金融商品なのです。
投資信託は大きな意味では「ファンド」のひとつですが、みなさんが安心して投資できるよう行政によってしっかり管理された商品といえます。
投資信託の値段ってどうやって決まるの?
「基準価額」が投資信託の値段です。でもこれら「基準価額」はどうやって決まるのでしょうか?株価のように絶えず動くものなのでしょうか?
投資信託の基準価額は、次のように決まります。
- 投資信託が投資している全ての資産の時価の合計に利息・配当収入を加えます。
- 信託報酬等、必要な費用を差し引きます。分配があった場合は分配金も差し引き、「純資産額」を計算します。
- 2.で計算された金額を、投資信託全体の口数で割ります。
基準価額とは「投資信託の時価」です。正確には、この基準価額の計算では、まず投資信託が投資しているすべての資産(株式や債券など)を毎日の値段(時価)で評価します。次に、株式や債券などの利息や配当などの収入を加えます。
そこからさらに手数料などの費用を差し引いて「純資産額」というものを計算します。この「純資産額」はいわば、投資信託の規模を表します。
そして最後に、純資産額を投資信託全体の口数(受益証券の総口数といいます)で割り、「投資信託の1口当たりの価額」を算出しますが、これを「基準価額」と呼んでいます。なお、1口=1円のファンドは1万口当たりの価額、1口=1万円のファンドは1口当たりの価額で示されています。1口がいくらかが分からない場合には、投資信託説明書を見て確認することもできます。
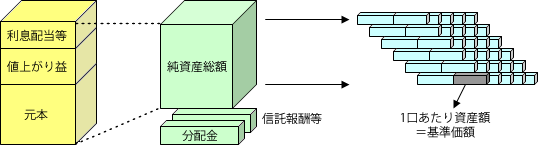
投資信託は、株や債券など値動きのある有価証券に投資をする金融商品ですから、毎日その時価は変わります。ただ、株式のように証券取引所が開いている間中、絶えず変わるわけではなく、その価額、「基準価額」は、1日に1回計算され、発表されます。
投資信託の基準価額を知る方法としては、次の3つがあります。
- 運用会社、販売会社、評価会社のホームページで提供されている情報を利用する。
- 運用会社や販売会社に電話で確認する。
- 新聞で確認する。
投資信託の選び方
投資信託は他の金融商品とどうちがうの?預金や株式との違いは?
投資信託にはたくさんの種類がありますが、預金や株式と比べると決定的に違う点がいくつかあります。このような特徴を抑えておくと、投資信託とは何かがわかってきます。預金や株式との違いをあげてみましょう。投資信託の特徴をつかんでみて下さい。
<預金と違うところ>
- 預金は元本保証ですが、投資信託は元本が保証されていません
- 預金は利回りがあらかじめ確定していますが、投資信託は運用成果によって収益が変動します
- 預金は銀行のみしか扱っていませんが、投資信託は銀行以外にも証券会社、郵便局、生命保険会社などでも扱っています
<株式と違うところ>
- 株式を買うにはある程度のお金が必要となりますが、投資信託は小口の金額で買うことができます
- 投資信託は株式だけでなく債券にも振り分けて買うことができ、安全性を高めることができます
- 株式はみなさん個人で銘柄の選択をしたり、売り買いのタイミングを見極めなければなりませんが、投資信託では専門家に運用の全てを任せることができます
- 株式はどこの証券会社でも品揃えが同じですが、投資信託は販売会社によって品揃えがさまざまです
投資信託は元本が保証されていませんが、様々な種類が用意された優れた金融商品です。なかには株式に比べ安定運用に配慮しつつ、高い収益が期待されるタイプや、毎月分配金の出るタイプなどもあります。
投資信託の種類
2024年末時点で、約6,000本もの公募投資信託があり、それらは投資する対象や投資の方針などによってバラエティに富んでいます。ただ、これらの種類を把握しておくことはその投資信託の特徴にも直結するため、とても重要です。また、投資信託を選ぶときにもとても参考になりますので、自分の買おうとしている投資信託の種類を確認することをおすすめします。
主な分類方法として次の5つがあります
- 運用する対象――株式投資信託・公社債投資信託
- 追加の設定が「できるか」、「できないか」
- 投資の方針
- 収益を分配「するか」、「しないか」
- 設定された国
投資信託を買う前に、その投資信託がどんな種類なのかを確認してみましょう。また、同じ分類の投資信託でもどういう運用方法を使っているのか確認してみることが大切です。投資信託にはさまざまな分類方法があります。いろいろな角度から投資信託を比べた上で一番自分に合うと思われる投資信託を選びましょう。
投資信託を選ぶポイント
さまざまな投資信託の中から自分に合う投資信託を選ぶのはなかなか大変なことです。そこで投資信託を選ぶ基本的なポイントをあげてみました。
- ステップ1.自分にあった投資信託のタイプを決定します
- ステップ2.次に、そのタイプのなかから、投資信託を選択します
ステップ1.目標を決め、大まかに投資信託のタイプを決めましょう。
投資信託を買う前に、あらかじめ、みなさんの投資目標を決めておきましょう。教育資金なのか老後の準備金なのか、その目的によって必要とする金額は異なってきますし、運用の安全性の程度も変わってきます。
投資信託の運用対象はさまざまです。国内の株式や債券以外にも海外の株式や債券などで運用する投資信託があります。また、それらを組み合わせた運用も可能です。そのため、投資信託を通じてさまざまな運用目標に対応することができます。
ステップ2.同じタイプのなかから投資信託を選択します。
つぎに、具体的な投資信託を選びましょう。選ぶときには次の6つのポイントを確認します。
チェックポイント
- □ 運用成績
- □ コスト(費用)
- □ 純資産残高
- □ 残りの運用期間
- □ 株式売買比率
- □ 運用する人(ファンドマネジャー)
ポイント1.運用成績
(1)3年以上の運用状況を確認する
運用成績を見るとき気を付けなければならないのは、設定されてから3年たっていない投資信託です。運用成績を比べるには、その期間が3年未満では十分な判断ができません。たまたま、その時の市況が良かったからかもしれないからです。このため運用成績を比較する場合は、最低でも3年、できれば5年以上の運用状況を確認するようにしましょう。
(2)ベンチマークや似ているファンドと比較する
また、運用成績を見るときは、何%上がった、下がったという収益率のほかに、ベンチマークや似ている投資信託との比較もおおいに参考になります。たいていの投資信託は、その投資信託の成績を比べるための指数(これをベンチマークといいます)が設定されています。指数は、その投資信託が投資している市場全体の動きを表しており、この収益率よりも高いか低いかで市場全体よりも運用が良かったか悪かったかがわかります。また、似たような投資信託(ライバルファンド)の運用成績と比べることでも、その投資信託を運用するファンドマネジャーの腕がわかります。
(3)投資信託の値動きの大きさもチェックしましょう
結果が良すぎる投資信託は、その分リスクを大きくとって運用している可能性があります。投資信託の値動きの大きさは「標準偏差」でチェックできます。数値の大きい投資信託ほど値動きが大きい投資信託であるといえます。基準価額の動きが大きい投資信託は、長期的に安定した高い収益が出せない可能性が高いと判断されます。小さいリスクで大きなリターンがベストです。
ポイント2.コスト(費用)
投資信託は買ったとき、売ったとき、そして持っている間にも費用がかかります。どのタイミングで費用が高く設定されているかは投資信託ごとに異なるため、注意が必要です。買ったときの手数料が無料でも、解約時に高い手数料がかかったということでは、なんのために安い手数料の投資信託を探したのかわからなくなってしまいます。そこで、購入前に買ってから売るまでにかかる費用を比較することが重要です。
投資信託にかかる費用としては、「販売手数料」、「信託報酬」、「信託財産留保額」、「有価証券売買手数料」「税金」などがありますが、なかでも「販売手数料」と「信託報酬」は投資信託の二大コストといわれており、特に注意が必要です。
投信の二大コスト
- 販売手数料:商品説明や投資相談の対価としてみなさんが販売会社に対して支払います。
- 信託報酬:運用の対価として「運用会社」に、資産の管理の対価として「信託銀行」に、解約や分配金の支払いなど事務管理の対価として「販売会社」に、みなさんが支払います。
一般的に投資信託の費用は債券型より株式型が高く、指数に連動する「インデックス型」より運用成績がファンドマネジャーの手腕にかかっている「アクティブ型」の方が高い傾向にあります。
また、販売手数料は買う販売会社によって異なるため、販売会社に出向く前に調べておきましょう。運用会社やウエルスアドバイザーのホームページで確認するとよいでしょう。
ポイント3.純資産残高
純資産残高はみなさんの投資した資金の合計、つまり、投資信託の規模を示しています。投資信託を安定的に運用していくためには、ある程度以上の規模が必要です。規模が小さいと多くの銘柄に資金を振り分けることができず、分散効果が小さくなったり、資金の出入りの影響も大きく受けるため効率的な運用ができなくなることもあります。
通常、純資産残高は30億円以上あったほうが安心できるといえます。さらに10億円を下回るようなら繰り上げ償還(途中で運用中止)の可能性も高まりますので注意が必要です。運用会社やウエルスアドバイザーのホームページで確認できます。
ポイント4.残りの運用期間
投資信託を購入する際、運用が開始されてからの期間と残りの運用期間を確認しておきましょう。運用してから3年が経過していない投資信託は、運用成績の比較が困難です。また、残りの運用期間が短い場合、運用がおろそかになる恐れがあります。できれば無期限もしくは残った運用期間の長い投資信託に運用する投資信託が望ましいでしょう。投資信託説明書で確認できます。
ポイント5.株式売買比率
株式売買比率とは、投資信託に組み入れている株式や債券を売ったり買ったりする頻度を表す指標です。株式売買比率が低ければリスクを抑える傾向にある投資信託、高ければ積極的にリスクを取りにいく傾向のある投資信託といえます。売買すればコストが増え運用成績が悪化しますので、この数値は低い方が望ましいといえます。直近の運用報告書で確認しましょう。
ポイント6.運用する人(ファンドマネジャー)
ファンドマネジャーが変われば、その投資信託に対する考え方や運用が変わる可能性があります。安定運用の面からファンドマネジャーの変更は望ましいことではありません。なお、ファンドマネジャーの運用経験年数もできれば確認しておきたいポイントです。5年以上の運用経験年数が望まれます。
投資信託の購入後
投資信託の情報の確認方法は?
投資信託の情報の確認方法は、Webサービスやスマートフォンアプリ等が主流となってきております。ウエルスアドバイザーではWebサイト、スマートフォンアプリとどちらからも基準価額やその他情報の確認が可能です。是非ご利用ください。
投資信託の運用状況を調べたいけれどどうすればいいの?
投資信託を買うときかなりの手間と時間をかけるわりに、買った後そのまま放っておく人が残念ながら多いようです。投資環境は常に変化しています。いくらプロに運用を依頼しているからといってそのままにしておかず、定期的に運用状況を調べるようにしましょう。そして、余りにも運用が同じようなタイプの投資信託に比べて劣るようであれば、解約することをおすすめします。
でも、運用状況は何をみて確認したらよいのでしょうか。
決算期ごとには詳細な運用状況が書かれた運用報告書が送られてきます。
月報や週報を定期的に見ましょう。
1.運用報告書
投資信託は年に数回決算を行いますが、そのタイミングで「運用報告書」が作成され、みなさんの手元に送られてきます。この「運用報告書」には、その期間の運用経過の報告や、どんな銘柄で運用したか、今後どんな見通しをもっているかなど、重要な情報が書かれています。なお、重要事項だけを記載した「交付運用報告書」と詳細な事項を記載した「運用報告書(全体版)」の二段階で発行されます。
運用状況の主なチェック項目
- □ 運用実績
- □ 運用経過
- □ ファンドマネジャーのコメント
- □ 組入有価証券明細表
- □ 今後の運用方針
2.運用レポート
運用報告書は、運用状況を詳細に知ることができますが、決算日ごと(ただし、毎月決算型や隔月決算型、3カ月決算型の場合は6カ月ごと)にしか知ることができません。
もっと短い期間で運用状況をチェックしたい場合は、運用会社が出す週報や月報が参考になります。週報と月報を両方出す投資信託は、月報の方が週報に比べて詳細な情報となっていますので、通常は月報を見て、少し動きがあるときや心配なときや、できるだけ早く投資信託の情報が知りたいときなどに週報を見るのがよいでしょう。これら週報や月報は、運用会社のホームページでたいてい手に入れられますが、出ていない場合は、販売会社に問い合わせてみるといいでしょう。
3.その他
投資信託の値段である「基準価額」が大幅に変動したとき、運用会社のホームページに「臨時レポート」が出ることになっています(概ね5%変動した場合に出るようです)。「臨時レポート」には、大幅に変動した理由、今後の見通しなどが書かれています。急に「基準価額」が下落して、慌てて解約するよりも先に、こういったレポートを読んで、冷静に対処することが必要となるでしょう。臨時レポートについては「臨時レポート」をご覧ください。
投資信託は値動きのある商品に投資しているので、買った後のアフターフォローも重要となります。投資信託の商品性に変化はないか、自分で決めた資産配分どおりになっているか、定期的にチェックしておくことをおすすめします。
投資信託は長期保有が原則
投資信託へ投資するなら長期に保有したほうがよいとよくいわれますが、なぜでしょうか?その理由は、長期で投資することによって、いくつかのメリットを受けることができるからです。さあ、時間を味方につけて運用成果を高めていきましょう 。
長期保有のメリット
- 長期保有は複利の力を取り込むことができます。
- 長期に保有すると運用のリスク(値動きの幅)が縮まります。
- 長期保有はコストの負担を軽くできます。
1.長期保有は複利の力を取り込むことができます。
長期で運用する最大のメリットは、複利の力を最大限に発揮できるという点です。これは長い期間、投資を続けていると、途中に発生する利子や分配金などを再投資することができ、利子や分配金にも利息をつけることができるためです。このように長期投資は複利の効果を最大限に取り込むことができます。
2.長期に保有すると運用のリスク(値動きの幅)が縮まります。
投資信託を5年、10年と長く持ち続けると、値動きの幅(リスク)が縮まってくることが知られています。値動きの幅が縮まるということは、安定した運用が行われるということです。長期に保有した方が、リスクの管理が行いやすいといえるのです。
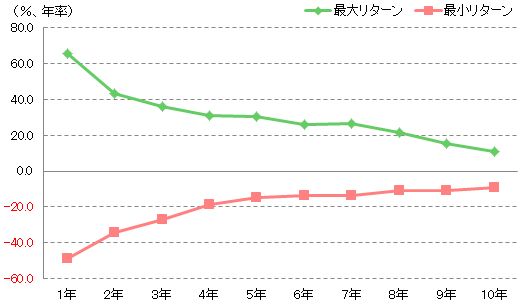
横軸が投資した期間、緑の線がその期間中で最もよかった運用成績、
ピンク色の線がその期間中で最も悪かった運用成績です。
緑とピンク色の線の幅が広ければ広いほど、その期間内の値動きが大きいことを示します。
長期で持てば持つほど、緑の線とピンク色の線の差は縮まり、値動きが小さくなっていることがわかります。
3.長期保有はコストの負担を軽くできます。
長期に投資信託を保有するメリットの一つには、購入時、解約時にかかってくる手数料の負担を軽減する効果もあげられます。投資信託の購入手数料が3%だったとしましょう。運用期間がわずか1年だとせっかく出た収益に与えるマイナスの影響は3%ですが、運用期間が3年だと3年平均にならされ1%となります。このように長期で保有すればマイナスの影響は縮小していきます。
パフォーマンスの評価
・トータルリターンの計算法
リターンというのは投資による収益のことですが、ここではパフォーマンスを測定するうえでよく使用される「トータルリターン」の考え方とその計算方法について触れてみましょう。トータルリターンとは、収益分配と値上がり益の推移を測定した数値です。但し、その計算方法は、収益分配金の取り扱いにより大きく分けて2通りあります。
- 収益分配金を分配時に全額再投資したものとして計算する。
- 収益分配金を受け取り最終時点の基準価額に加算し計算する。
ウエルスアドバイザーでは、ファンドの長期投資をすすめ、いかに再投資による複利効果が大きいかを重視するため、(1)の方法で計算します。これは、収益分配金を分配時に再投資したと仮定し、トータルリターンの算出を行います。基準価額を利用することから販売・募集手数料、換金手数料は控除されていませんが、間接的なコスト(信託報酬、売買委託手数料、など純資産から控除されるもの)は控除済みのリターンとなっています。表示する場合は年換算値とするのが通例です。年換算とは、例えば3年間のリターンを1年あたりのリターンとして計算する方法で、他のファンドや金融商品と比較する場合によく用いられます。3年で9%のリターンがあるものは、年換算で2.914%のリターンとなります。
ただ、一定の期間で計算するトータルリターンは、ファンド間の比較に使用するもので、大切なのは自分にとってのトータルリターンがどのくらいになっているかです。ファンドをいつ購入し、実際に分配金は再投資したかどうかによって、みなさん自身のトータルリターンは変動します。
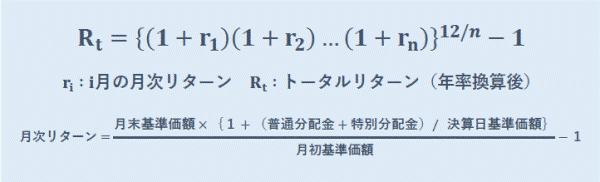
色々なパフォーマンス評価
ファンドのパフォーマンスの測定は、単にリターンを測定するだけでは十分とは言えません。ファンドのリターンが高くても、それはファンドマネジャーがリスクの高い投資をした結果、達成されたのかもしれないからです。このようにパフォーマンス測定を見る場合、リスクに見合ったリターンが他のファンドと比較してどうかということが重要です。
それではまずファンドのリスク尺度について見ていきましょう。
・標準偏差
標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離(かいり)した結果となる可能性が高くなります。また、カテゴリーの中でファンドの標準偏差が平均以上なのか以下なのかを確認して下さい。
・カテゴリー内リスク
ウエルスアドバイザーでは、ファンドのリターンが特定の金利水準を下回った時だけをリスク(下方リスク)と考えます。上回った時はリスクとしてとらえません。カテゴリー内リスクの計算は、リスクがないと想定される特定の短期金利(無担保コール翌日物)と、ファンドの月次リターンを比較することで行います。具体的には36カ月の間に、ファンドの月次リターンが短期金利を下回った月の下回ったパーセンテージを合計し、さらに合計数字を対象期間の月数(36)で割って、月次の平均数値を求めます。こうして求めた下方乖離幅(かほうかいりはば)をそのファンドが属する小分類の平均値と比較します。実際には小分類の平均値で割ることにより、平均との相対価(リスクスコア)を求めます。(式については後編に記載のファンドレーティング値欄を参照)
次に、上記のリスクを考慮した「リスク調整後のパフォーマンス測度」について説明します。
・シャープレシオ(シャープ測度ともいう)
シャープレシオはリスクに見合ったリターンを得ているかを表す指標でリスク尺度にリターンのぶれの大きさ(標準偏差)を使用します。数値が大きい方が高い評価となり、ウエルスアドバイザー社以外の多くの投信評価会社が採用しています。
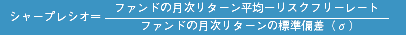
・ファンドレーティング値
ファンドレーティング(☆印での5段階評価)は、ファンドのリスク調整後パフォーマンスの総合評価を小分類中で比較して評価しますが、その基になっている数値がファンドレーティング値です。運用成績が3年以上のファンドを対象として、過去3年間のリスク調整後のパフォーマンスを次の式で求めます。
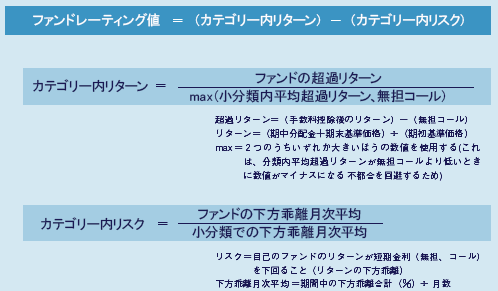
・その他パフォーマンス評価
アクティブファンドのように、特定のベンチマークを上回る成果を目標としているファンドには、そのベンチマークを実際何パーセント上回っているかどうかを見ることも、重要なパフォーマンス評価の1つと言えます。
投資は「自己責任」
投資を行う上で、忘れてはならないのが「自己責任」の原則です。1996年の「金融ビッグバン」で、みなさん一人一人が資本市場に参加しやすくなったかわりに、参加するみなさんには「成功しても失敗しても、自分の責任は自分でとる」というルールが徹底されました。
投資するときにみなさんが、取引の投資判断を誤り、損失を受けたとしてもそれは全てみなさん自身が負担するという原則のことを「自己責任」といいます。
「自己責任」を簡単に言えば、自分で考えて行動し、その結果についての責任も自分で負う、ということです。銀行預金と異なり、常に「危険性」の伴う証券取引においては、どこに「危険性」があるかを知り、その「危険性」を避けるために何が必要で、何をすればよいかを、みなさんが自分で考えて自分で決めなければなりません。
もちろん、この自己責任が成り立つためには、資本市場の公正性が確保されていなければなりません。このため、「投資家保護」、「情報開示(ディスクロージャー)」、販売する側の「説明責任」などの法制度も整備されつつあります。
これからは、預貯金にお金を寝かせておくにしても、積極的に運用するにしても、その商品の特徴を理解しておくことが必要です。基本的な特徴をつかんでおくと、この金融商品は「景気が悪くなっても大丈夫そうだ」、とか、「この金融商品は、株式の性格が強そうだ」といった見方ができるようになります。また、特徴がよく理解できない場合は、その金融商品に手を出さないことが賢明です。
